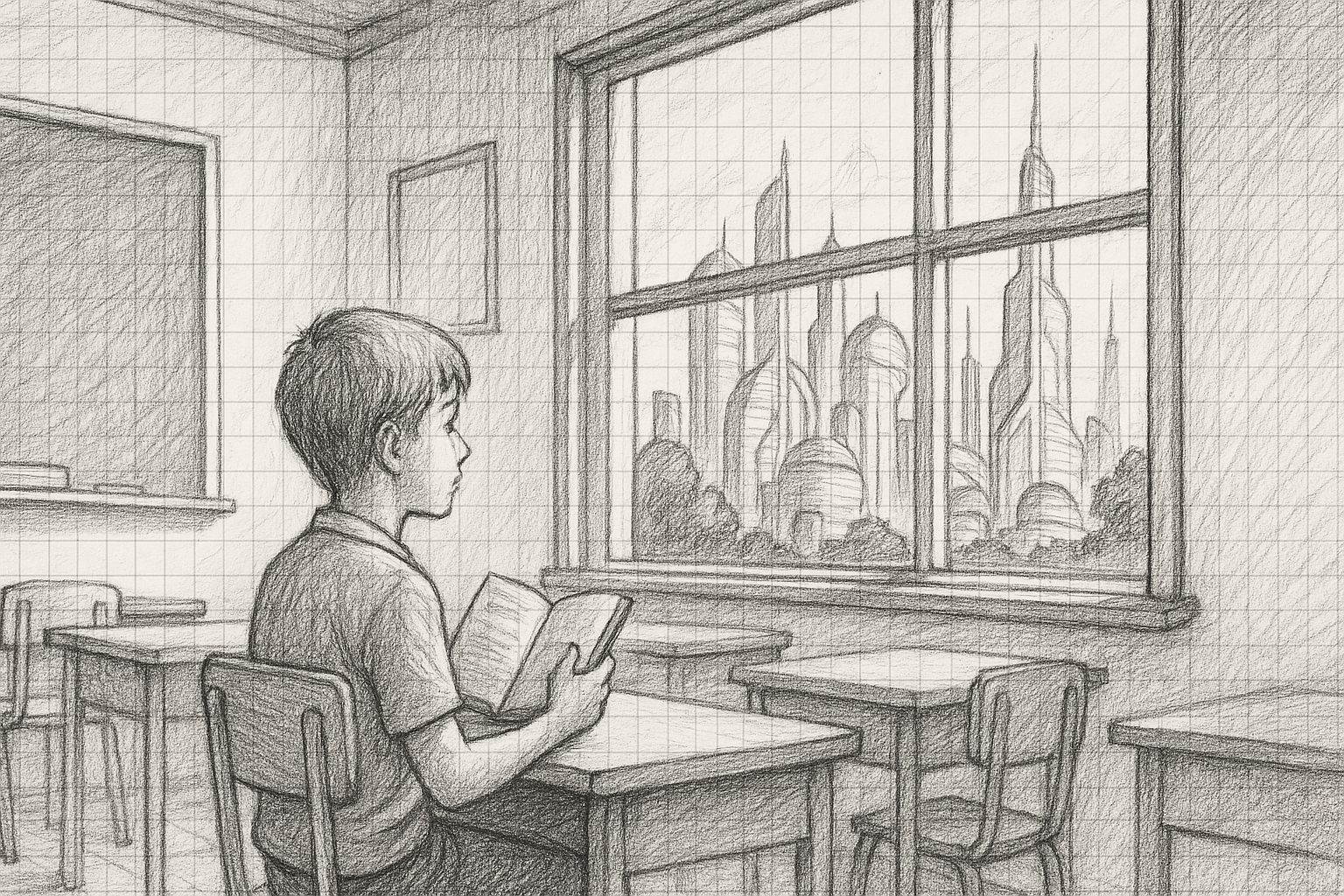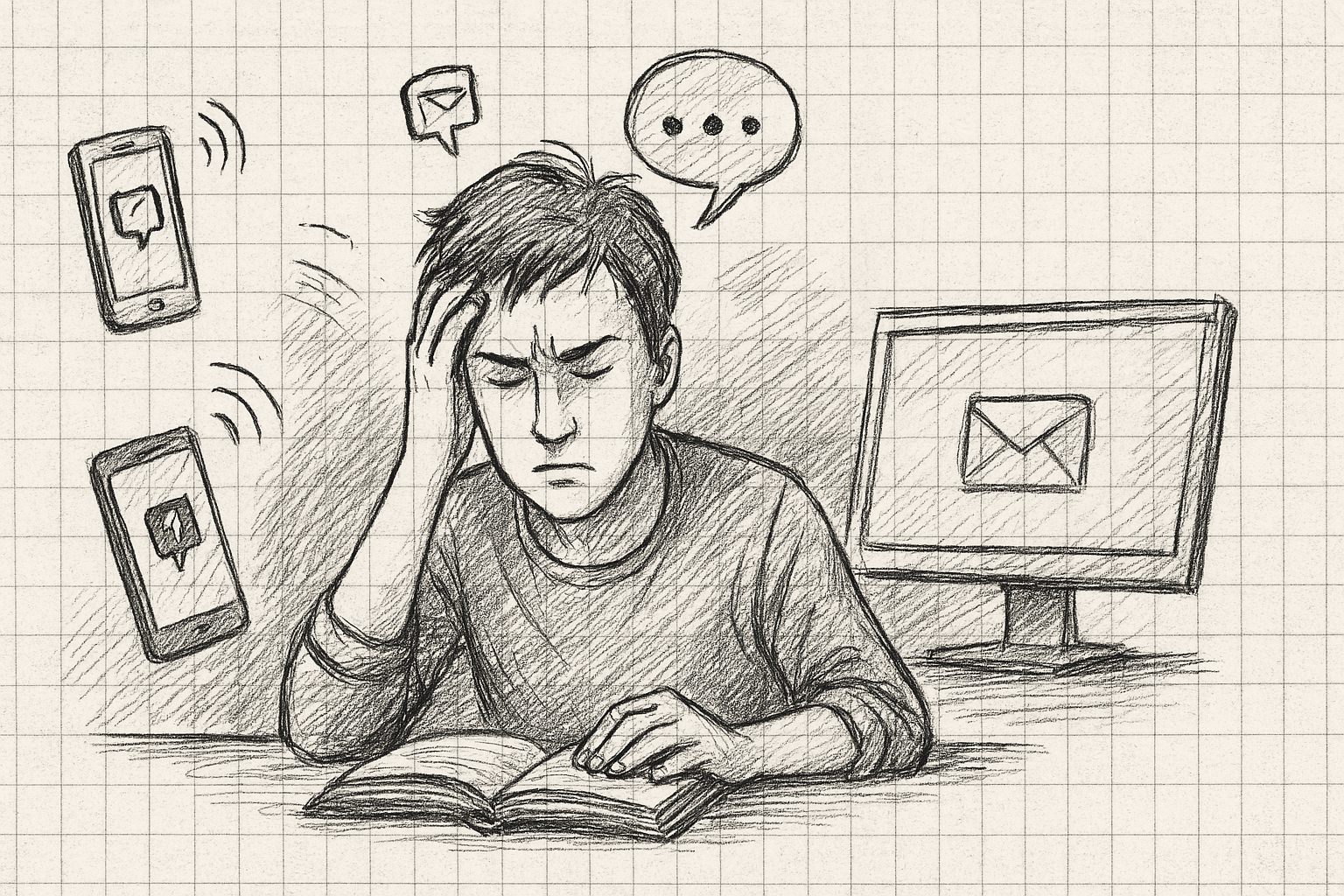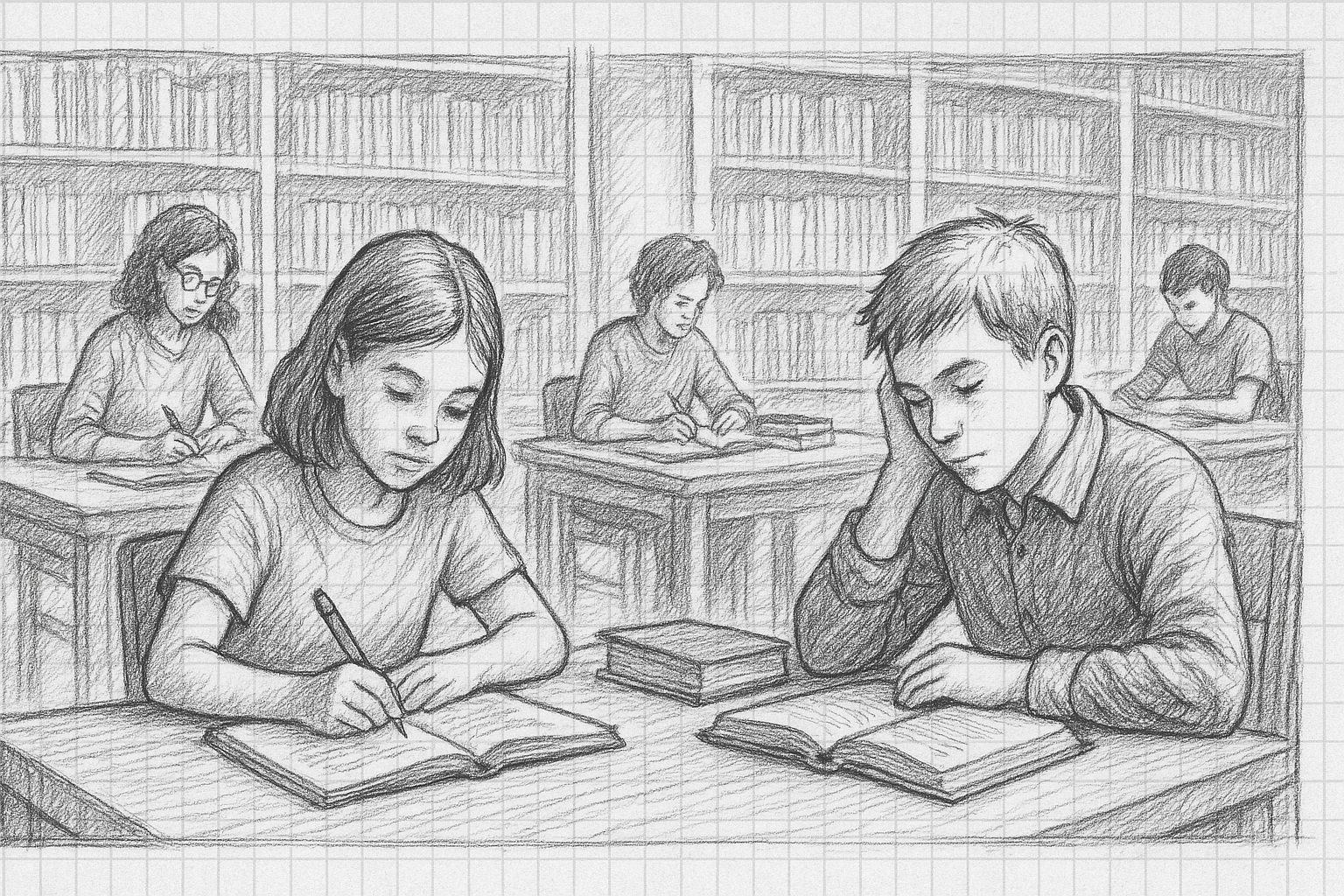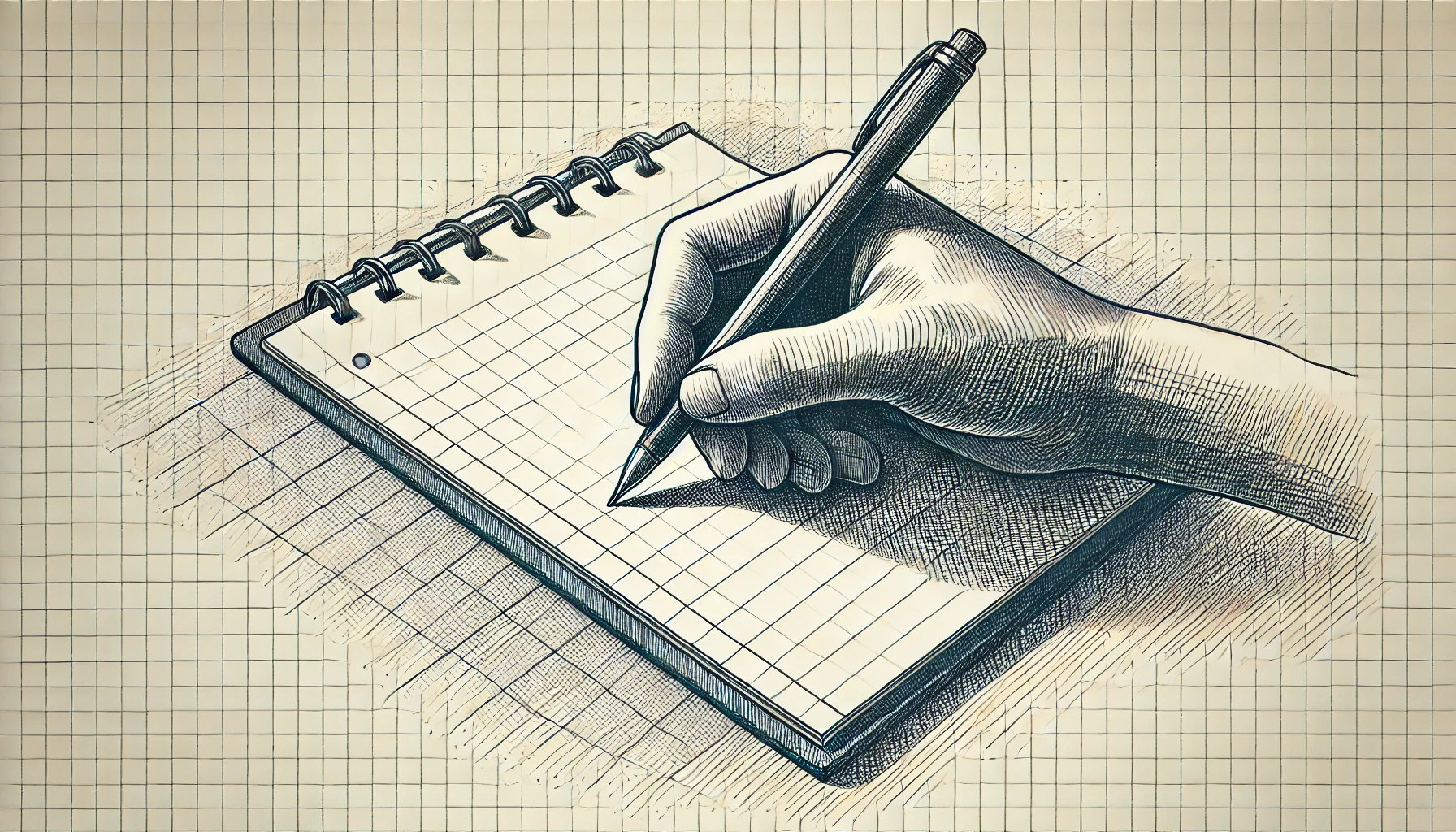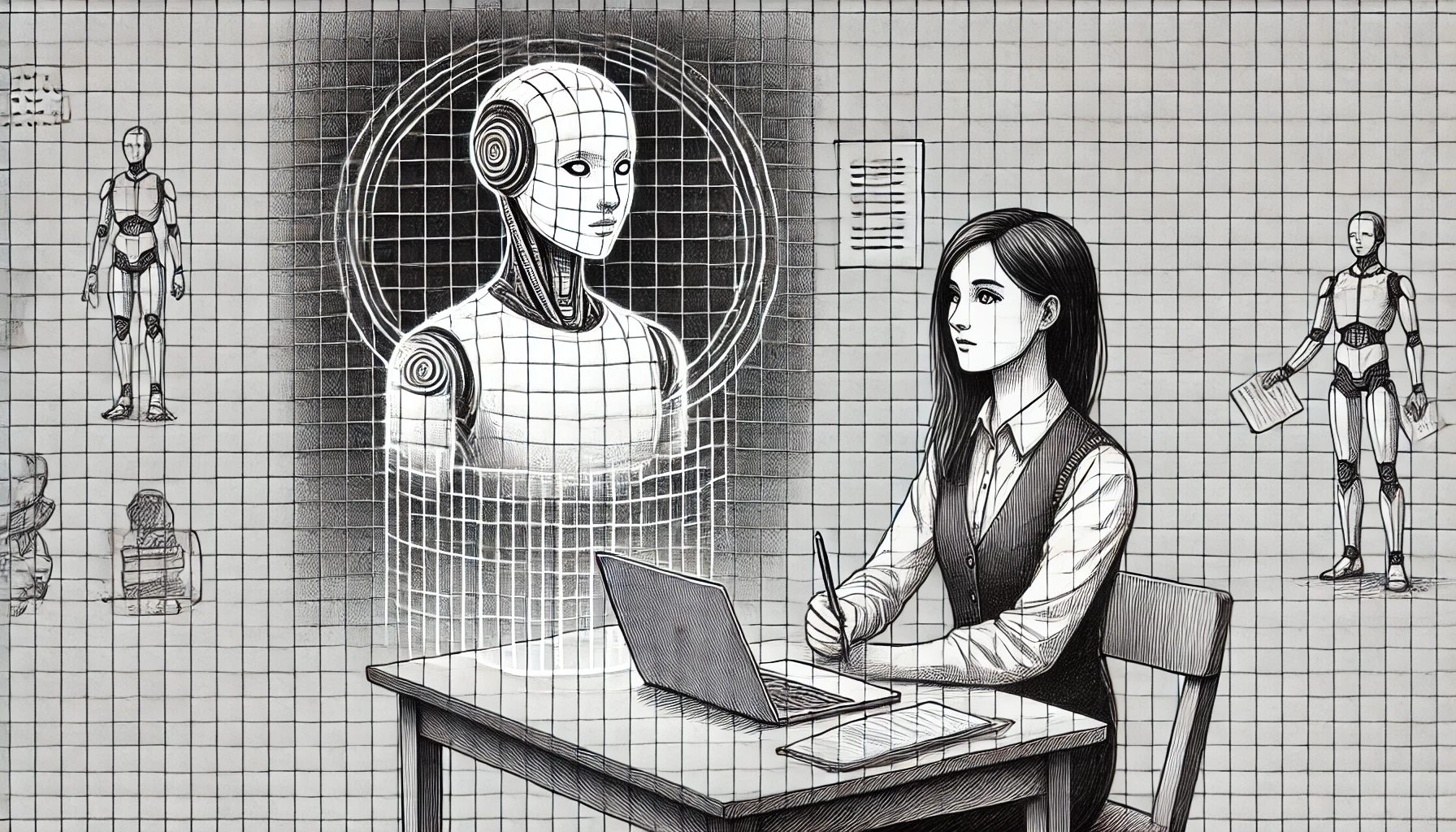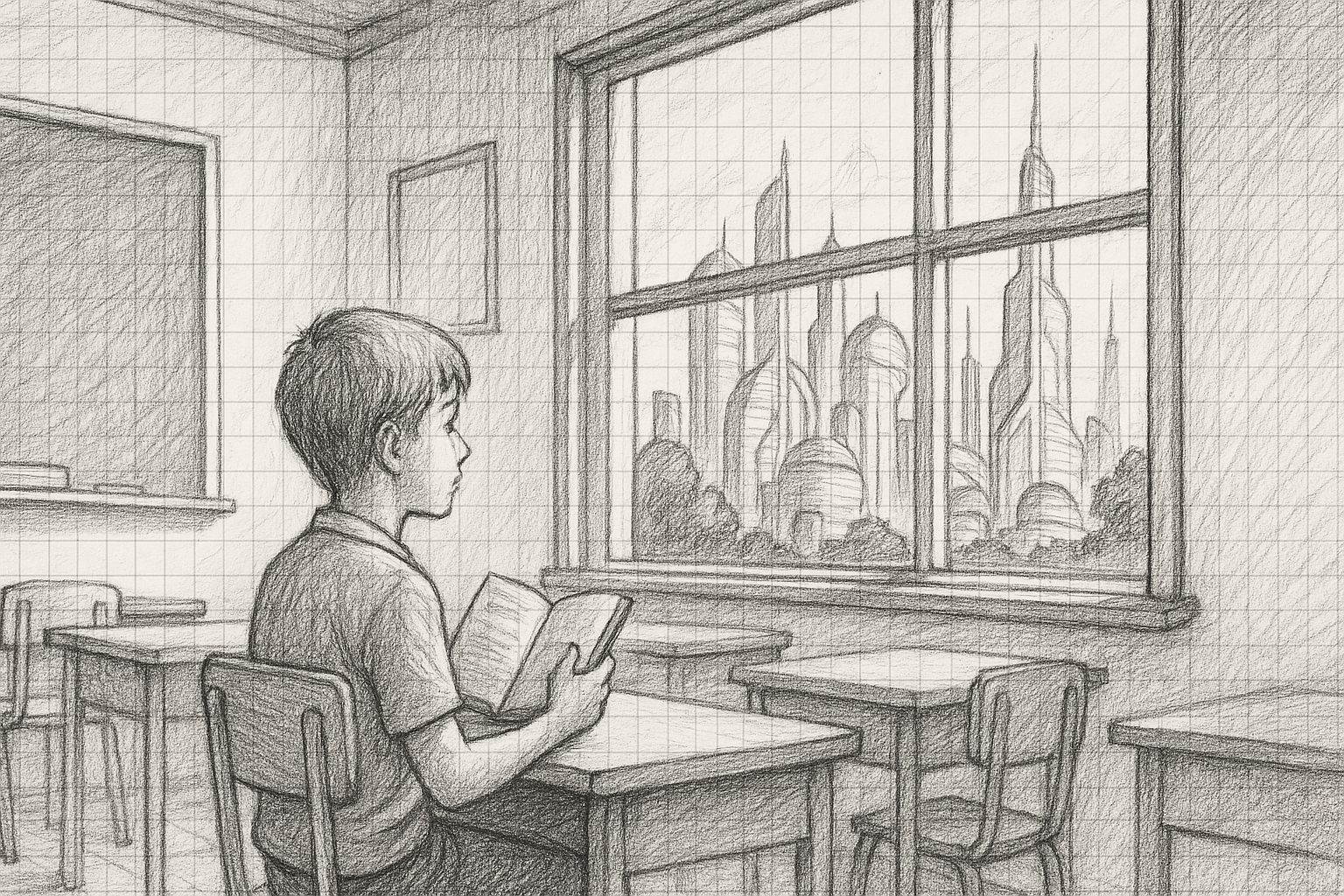
AI時代における教育の再考:学校の本当の目的とは?
AIが急速に定型的な認知作業を自動化していく中で、暗記や標準化テストに重きを置いた従来の教育は時代遅れとなりつつあります。AIが支配する職業に学生を備えさせるのではなく、学校は創造性、批判的思考、感情的知性、倫理的思考といった人間特有の能力を育むべきです。未来の学びは、自分のペースで進める情熱駆動型の学際的な教育を重視し、固定された職業ではなく変化に適応する力を育てることになるかもしれません。教育の期間は短くあるべきか、それとも生涯にわたるべきか?知識の丸暗記ではなく、知恵をどう評価するべきか?といった重要な問いが残されています。AIの台頭は教育を不要にするのではなく、知識の伝達から人間の豊かさの育成へと転換することを求めており、次の世代が機械と共に繁栄するための道を切り開くのです。
この記事を読む
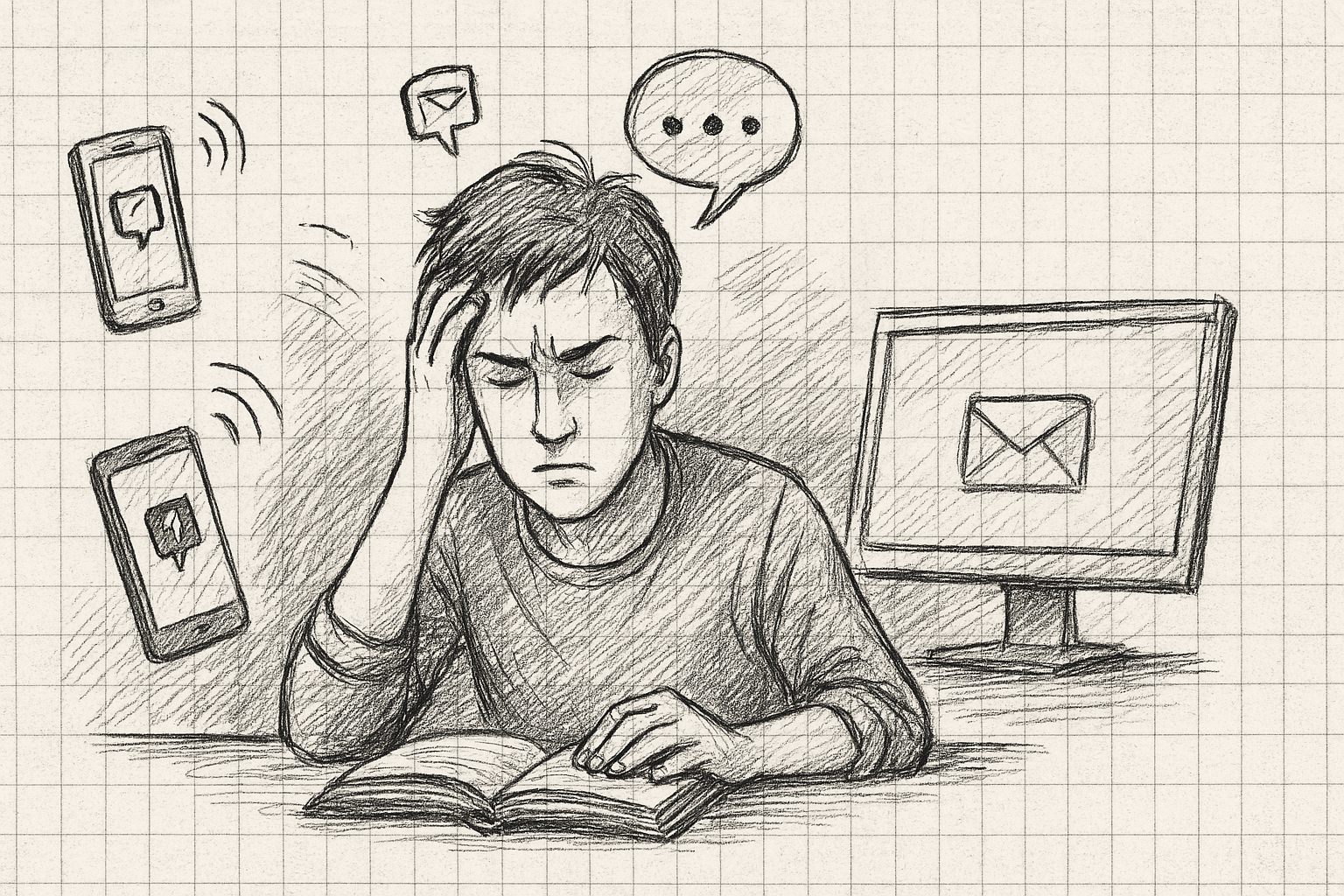
現代における集中力の危機:思慮深い探求
現代の生活は、私たちの集中力を著しく蝕んできた。学生、教師、親、そしてあらゆる職業人が気の散漫に苦しんでおり、その原因は単にスマートフォンにあるのではなく、ドーパミンを利用した設計、乱れた食生活、睡眠不足、そしてマルチタスクを美徳とする文化といった、より根深い要素にある。アーミッシュのようなテクノロジーに抵抗する共同体とは異なり、私たちの多くは断片化された状態に置かれ、記事を流し読みし、作業を次々と切り替え、絶え間ない刺激を求め続けている。その本当の代償とは、仕事や人間関係、そして自己内省における「深さ」を失ってしまったことにある。テクノロジーそのものが悪いわけではないが、私たちとそれとの関係性は再評価されるべきである。集中力とは単なる生産性の問題ではなく、「今ここ」に存在する力である。問いは残る――私たちは注意力を取り戻せるのか、それとも永遠の気晴らしが新たな常態となるのか?その答えは、意図的に生きるという姿勢の中にある――ただし、まずは自分たちが何を失ったのかに気づくことが必要だ。
この記事を読む
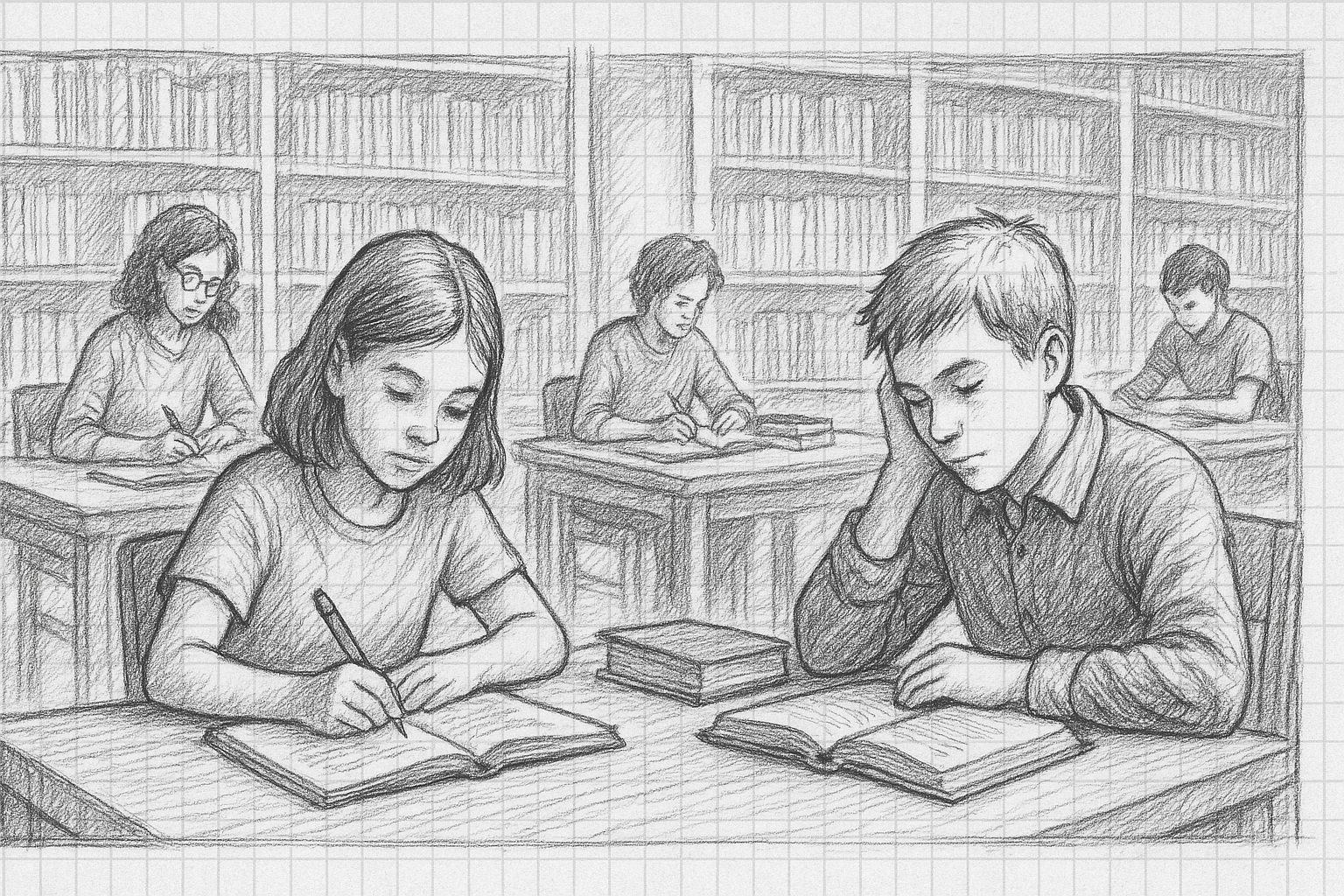
宿題を再考する:現代教育におけるその役割についての考察
現代教育における宿題の役割は、再検討するに値します。宿題には、間隔を空けた復習によって学習を強化し、規律を教えるという利点がある一方で、批判者たちは、ストレスや不平等、そして効果の逓減を引き起こすことが多く、特にAIの登場により剽窃が容易になった現代ではその問題が深刻化していると主張します。反転授業やプロジェクト型学習、あるいは宿題を廃止する方針など、さまざまな代替アプローチも提案されています。重要な問いは、宿題が存在すべきかどうかではなく、それが本当に深い学びを支えているのか、それとも時代遅れの方法を単に繰り返しているだけなのかという点です。明確な結論を求めるのではなく、今こそ教育がどのように変化に対応し、生徒たちのためにより良い形へと進化できるかを考えるための省察が求められています。
この記事を読む
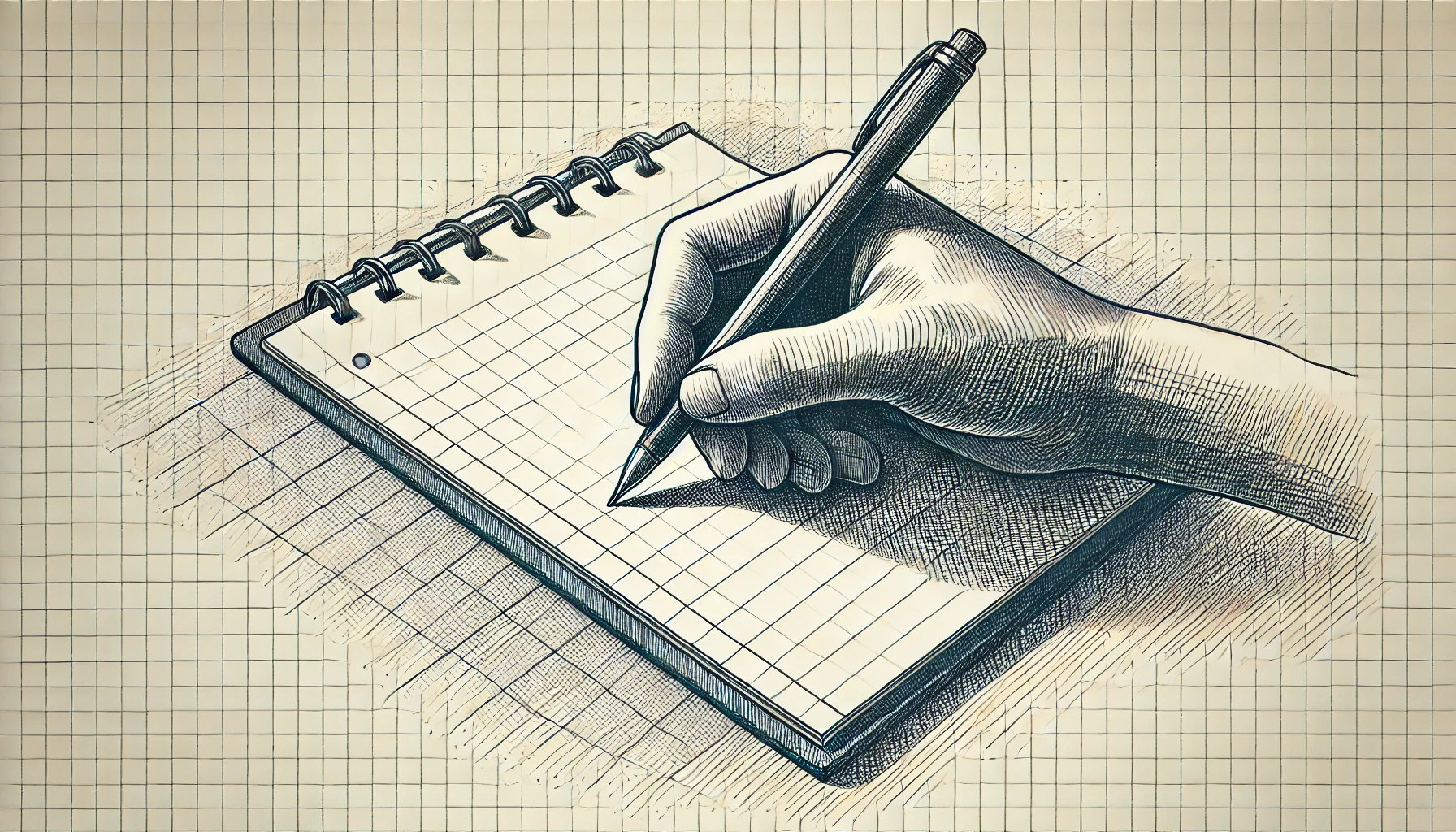
教育における手書きの不変の重要性:なぜもっと奨励すべきなのか
手書きは、タイピングでは再現できない認知的・感情的・創造的な利点を持つ、教育において依然として重要なスキルです。手書きは記憶力や批判的思考力、微細運動能力を高め、学習内容へのより深い関与を促します。また、創造性や自己表現、マインドフルネス(心の静けさ)を育み、スピード重視のデジタル社会に対する健全な対抗軸ともなります。教育者は日常の学習活動に手書きを組み込み、筆記体の指導や手書きの価値を自ら実践することで、生徒が集中力、回復力、そしてバランスの取れた学びの姿勢を育む手助けをすべきです。手書きを優先的に取り入れることによって、生徒たちに学問的・個人的成長に必要な本質的なスキルを身につけさせることができるのです。
この記事を読む
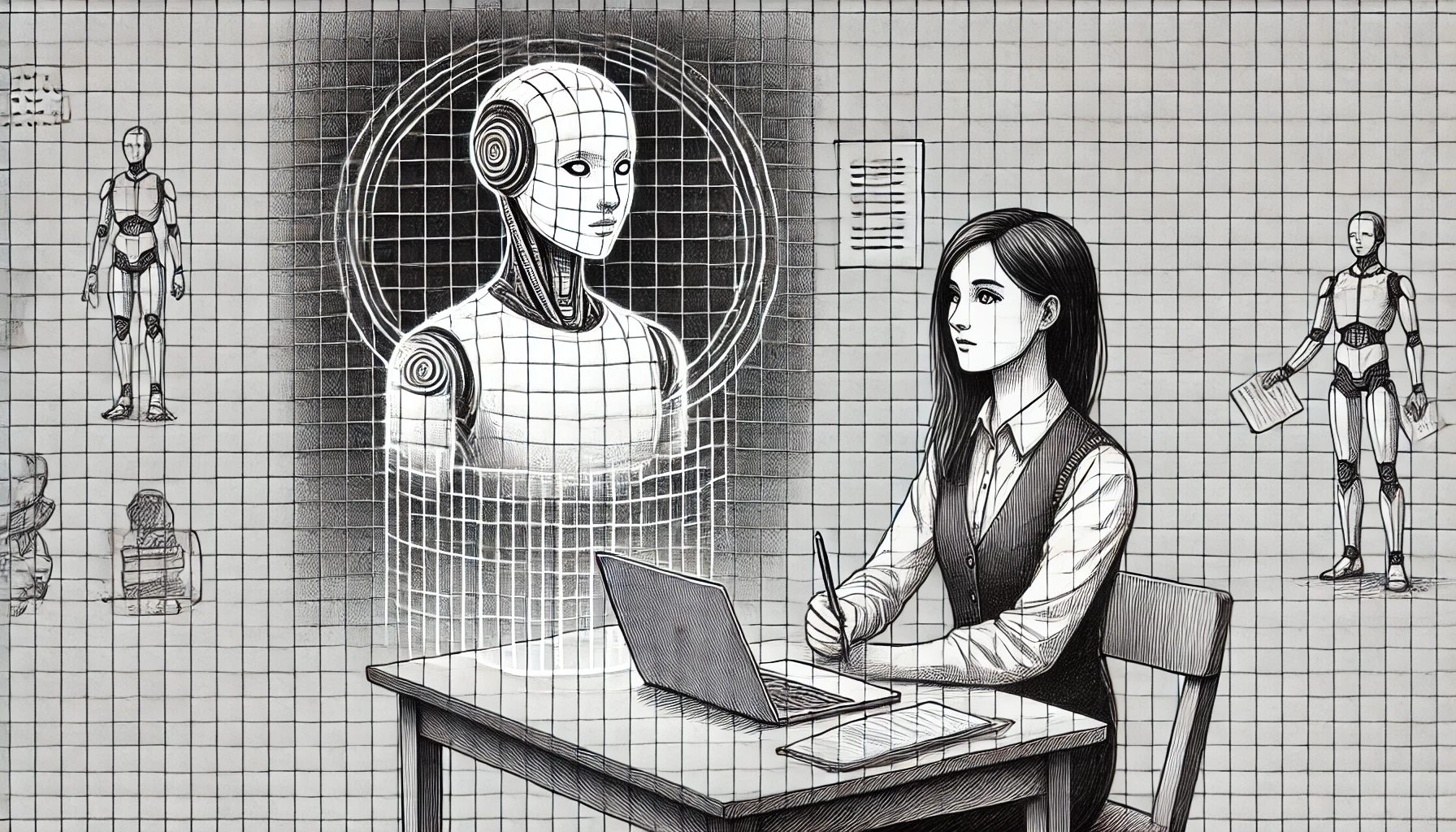
AIのジレンマ:学術課題で人工知能を使うのは「不正行為」か「革新」か?
教育分野におけるAIの台頭は、「ChatGPTのようなツールの使用は不正行為なのか、それとも次世代の問題解決能力の活用なのか」という議論を巻き起こしています。過去には電卓やインターネットといった革新も同様の懐疑の目で見られましたが、最終的には学びに不可欠な存在となりました。AIは、適切に使えば批判的思考や創造力を高める可能性がありますが、一方で依存のしすぎ、公平性の欠如、学びの本質の希薄化といった懸念も残ります。AIを教育に統合しながら学問の誠実さを保つには、評価方法の見直し、倫理的な使用の推進、そしてテクノロジー主導の未来に備える教育が求められます。近道ではなく学習支援としてAIを受け入れることで、教育を変革しながらその本質的な価値を守ることができるのです。
この記事を読む